シンポジウム無事終了しました。
先週開催されたシンポジウムもお陰さまで無事終了いたしました。
三橋さんの貴重な基調講演
「脱近代化」がサブテーマになったパネルディスカション
コーディネーターの武者先生が、最初からキレていて
聞きごたえのあるシンポジウムになりました。
120名程の方にお越しいただきました。
本当にありがとうございました。
以下「松本都市デザイン学習会」山田さんが書いて頂いた議事録です。
◆松本まちづくりシンポジウム◆
「中心市街地の問題とこれからの松本ビジョン」
日時 8月29日(月) 19時~21時
場所 松本市中央公民館 6階ホール
主催:ナワテ通り商業協同組合+なわて通りプロジェクト
共催:松本都市デザイン学習会・松本市中央公民館
参加者:120名

●第1部
基調講演「中心市街地の問題とこれからのまつもとビジョン」」講師:三橋重昭(NPO法人まちづくり協会理事長 経済産業省商店街再生ネットワーク専門委員
中心市街地商業活性化アドバイザー)
松本は、何度か訪れているが、松本城・山岳景観・文化の香り豊かな印象を持っている。
この講演では、全国の事例を交えながら、これからの松本のまちを考えていきたい。
講演は、以下の項目に沿って話を進める。
・なわて商店街の印象・評価・課題
・小石川の新しいまちづくりの取り組み「小石川マルシェ」
・松本市の商業構造
・松本市の中心市街地を考える 脱近代化・脱商店街活性化
・カタクラモール
松本の中心市街地を歩いて、小路や蔵の街の佇まいのヒューマンスケールに感動した。
しかし、昭和50年代の区画整理された駅前地区には、商業中心の活発な印象が無い。
また、伊勢町を中心とした区画整理地区の商業者は、近代化建替えによる負債で疲弊があるだろう。
六九町は、商店街が廃れた街として、知られている。
この様に、松本は、美しい街である一方、多くの問題も抱えている。
●なわて商店街の印象・評価・課題東京商工会議所の商店街評価、370項目に従って、なわて商店街を分析してみた。
まち並みの魅力/4.45 まちの歩きやすさ/4.56 まちの使い易さ/4.50
まちの楽しさ賑わい/4.07 日常利便/2.83 広域集客/3.75 公益的整備/3.89
全国の商店街と比べても、高評価と言える。
特色としては、通年の昼間歩行者天国。歩いて楽しい魅力がある。
歩行者通行量も5000人~7000人と、松本中心市街地で7位/14調査
人口20万人の商店街として、とても高い数値(上田市の最高で2000人)
但し、店舗の月坪効率は10.1万円と低く、営業力強化が課題。
しかし、松本市全体売り上げの0.1%の小さな商店街が、
この様なシンポジウムを開く前向きな態度は、特筆すべき。
●小石川の新しいまちづくりの取り組み文京区公設市場など、S30年代までは、賑わっていた商店街の歴史がある。
バブル期の地上げ、マンション建設があったが、商店街はある程度存続してきた。
エンマ通り商店街は、現在、22店で、年間10億円の売り上げ。
4つの商店街があるが、もっと頑張れる筈である・・・新しいまちづくりの取り組みスタートのきっかけ。
若手の商店主を集め、H22年「小石川活性化研究会」・ワークショップを始める。
歴史と現状分析から、10年後の小石川を考え目指すべき姿をまとめる。
・ちょっといい普段(少し上質な生活)
・文京の玄関(後楽園に近接・地下鉄4線・コミュニティーバスの発着)
ビジョンを推し進めるプロジェクト「小石川マルシェ」
・「ちょっといい普段」を念頭に、産直の食材市場。源覚寺の境内で、700人 30万円の売り上げ。
・60代、70代が中心の既存商店街に対して、マンション居住の若い世代にアピールできた。

●松本の小売商業構造・松本全体、年間売上高3239億円、月坪効率は25.5万円で、ほぼ全国平均。
・郊外ロードサイド(国道19号沿い)年間売上高1203億円で、月坪効率28.9万円と高い。
・駅前・中心市街地は月坪効率15万円~20万円と落ち込んでいる。
この分析から、現在は郊外ロードサイドが商業的には中心である、という印象。
ショッキングな数値だが、松本商工会議所の統計・分析でも、この事実は認識されていない。
「松本市の中心市街地商業ビジョン」を拝見したが・・・
個店の魅力向上・・・個店が厳しい状態の中で、個店の頑張りに期待するのは非現実的。
人材・組織の構築・・・活性化基本計画から10年を経た現在でも、なされていない。
「商都松本」というおごりも過去のもので、現在の市民はそう思っていない筈。
中心市街地活性化基本計画も策定されていない。(県内では、長野・飯田・塩尻・上田が策定)
中心市街地活性化基本計画が必ずしも功を奏すとは言えないが、
金沢は行政を中心に成功、高松は丸亀商店街を中心に成功・・・成功例もあり、取り組む価値はある。
日本の商業全体で、商店数が減少し、大型店化する中で、
公共・民間・市民がタッグを組んだ新しいスタートが必要。
脱近代化(国土交通省主導の、車優先・道路拡幅・核店舗・共同化ビル等の都市近代化からの脱却)
脱商店街活性化(店が減り商店主が高齢化した中で、活性化は望めない)
やはり、中心市街地商店街は、活力が無ければならない。
●松本のビジョン・街なか観光・・・まちの資産を活かす。交流人口を増やす。 街なか観光の事例・・・長崎さるく博
・新しいレベルの組織(×商工会議所・×商連・×縦割り行政)
・ローカルイニシアチブ(松本市民がベースに)
・カルチャーハプニング(路地など都市の魅力の再発見・SKF・工芸の五月etc)
・アーバンネイバーフード(都市の中で新しい近隣を育てる)
・メインストリートプログラム(組織デザイン・経済活性化プロモーション)
・商店街から、生活街への脱却
●カタクラモール構想カタクラ工業大宮工場跡地のコンサルタント経験から、カタクラの街に対する良心は信じたい。
松本における8.36haの土地は、街なかと一緒に考えていくべき。
事例としては、ライフスタイルセンター(アメリカ)等が注目される。
カタクラを中心市街地の構成メンバーとして、
中心部 VS 郊外 の構図の中で考えるべき。
世界に誇れる、松本の中心市街地を構築していって欲しい。
●松本市の取り組みの紹介
「水辺のマルシェ」
発表者:上條(なわて通りプロジェクト「水辺のマルシェ」プロジェクトリーダー)
8月に、なわて商店街 女鳥川を舞台に、「水辺のマルシェ」を実施
「NO―JIN」という松本の若手農業者を中心とした組織を発足
農業をアート、農作物・農業加工品をアート作品として展開している。
対面販売(コミュニケーション)を大切に、新たな可能性を探っていきたい。
「水辺のマルシェ」では、多分野の人と協働し、
食卓プロデュースとして、食材・器・雑貨etc をトータルで提案したい。
今後、年内に4回の「水辺のマルシェ」を企画している。

●第2部:パネルディスカションコーディネーター:武者忠彦(信州大学経済学部准教授)
パネリスト:三橋重昭(NPO法人まちづくり協会理事長)
丸山悦男(前松本市建設部長)
倉澤 聡(都市計画家 工芸の五月事務局 松本都市デザイン学習会会員)
山本真也(ナワテ通り商業協同組合理事長)
[武者] パネルディスカッションでは、基調講演を踏まえ3つの論点で議論を展開したい
1.「都市の近代化」の終わり・・・なわて商店街から考える潮流の変化
2.ビジョンを考えるヒント・・・「時間限定」「地域性」「外部環境」
3.協働と組織化・・・ビジョンへのアプローチ
最初の論点、「近代化」は、ハード中心・グローバリズムの考えで進められてきたが、山本さん・・・なわて商店街の実践をとおして、どの様に感じているか?
[山本] なわて商店街で「カエルまつり」を行って10年になる。
信大・松大+商店主を主体として実践、全国でもめずらしい推進体制で進めてきた。
[武者] 新しいまちづくり主体の重要性を感じる。
丸山さん・・・行政から見たなわて商店街は?
[丸山] 松本市建設課でH3~なわて商店街に関わってきた。
S63「ふるさとの川」に認定され、H3事業許可。
武家地と商人町の境に明治期に四柱神社がつくられ、神社の露店として、なわてが始まる。
子供のころから、神道まつりの舞台として、女羽川の遊びとして、個人的な思い入れがある。
なわて商店街の魅力を再発見してみた
・水辺の行事と風物詩・・・女羽川、三九郎
・道幅の狭さ・・・商店主と買い手のコミュニティーを生む
・カエル・・・ユニークなキャラクターの存在
・通年昼間歩行者天国・・・人が主人公の町
建設にあたっては、河川法・道路法・建築基準法など、法規制のクリアに奔走した
特に、河川法に於いては、治水安全度と親水性の狭間で、国土交通省と様々な議論。
[武者] 風土・風物との連帯、法規制をクリアする熱意、これがポイント。
倉澤さん・・・工芸の五月の新しさは? 海外経験を通して?
[倉澤] 工芸の五月は、5年前に発足し、松本市と協働して3年になる。
クラフトフェアが前身であるが、交通渋滞・環境負荷など、迷惑イベントの側面もあった。
交通社会実験などを通して、市民に広く受け入れられるイベントに発展した。
多分野との協働が結果としてまちづくりに・・・これからのまちづくりでは、協働が大切。
都市近代化=車社会から脱却し、人が歩く、集まる、カルチャーハプニングが生まれる町に。
フランスに5年前に生活していたが、中心市街地に人が戻りつつある。
海外では、いち早く、都市近代化からの脱却がみられた。
[武者] 工芸の五月・クラフトフェアは自主的な草の根からの展開。
そこでは、主催者自らが活動を楽しんでいる様子が伝わる点が重要。
飴市・松本ぼんぼんも、かつては主催者の熱意があっただろうが・・・。
海外でも、歩ける街が大きな潮流になっている。
三橋さん・・・全国の潮流は? 事例なども・・。
[三橋] なわて商店街で参考になる事例として、伊勢のおかげ横丁がある。
赤福の社長がマネージメントしている通りだが、全国トップクラスの売場効率。
いすず川との一体感など、なわて商店街と通じるところがある。
なわて商店街は、「地域のニーズに合理性」があり法律が運用されたと考える。
川越・小布施・裏原宿の例で解る様に、「都市は人間の為にある。」
おかげ横丁は、一主体(赤福)による民間のマネージメントなので特殊例だが、
商店街のマネージメントに於いて、「やる気の無い店は去れ」という態度も大切。
商店街のリーダーには、個店と街の調整役を超えた、発想の切り替えが必要。
街のハードの近代化と共に、街のマネージメントの近代化、
「ディベロップからマネージメントへ」が重要。

[武者] 「ディベロップからマネージメントへ」は大切なキーワード。
基調講演でも話題になった「松本の商業ビジョン」を拝見したが、
私は、「松本」という単語が無い事に、地域性とビジョンの欠如を感じる。
若者は郊外ロードサイド中心、中心市街地とは何か? 世代による認識の相違も感じる。
二つ目の論点「ビジョンを考えるヒント」に関して、以下のキーワードを挙げる。「時間設定」・・・世代、時間のスパンの捉え方。10年後or 100年後?
「地域性」・・・松本では、どうする。
「外部環境」・・・経済動向、トレンド、低成長、震災後の日本を捉えて
これらを踏まえて、「ビジョンを考えるヒント」のアイデアを伺いたい?
[山本] 「なわて通りプロジェクト」を、市民・商店主・行政とでタッグを組んで考えてきた。
「なわて」を「松本」と置き換えて考える事でヒントが出てくるのでは・・・。
なわて商店街では、「道で遊ぶ」という理念・・・これは松本ビジョンのヒント。
[武者] 「道で遊ぶ・通りで遊ぶ」・・・松本らしさを感じる。コンパクトシティーの根拠になろう。
[倉澤] 地域性が、全国・海外への発信力を持つ。
松本の良さのひとつに、市街地に川が流れている点を挙げる。
私は、この頃、アレチウリの駆除に奔走しているが・・・皆、川を大切にしない。
湧水は、ここ何年かで認知され活かされてきている。
川も同様に大切にし、宝(都市資源)を磨く事が大切。
山岳景観も同様で、50年タームの都市を考えると、高層マンションは問題が多い。
[武者] 今の街の良さ=地域資源を活かす。アレチウリへの取り組みも50年タームの取り組み。
丸山さん・・・50年・100年タームでの取り組みは?
[丸山] 歩く街・歩ける街が、街を変えていく。
松本市でも、車社会から、人を主体にした街への転換を図っている。
なわて商店街でウォーキングをする親子の姿が微笑ましい。
それに対して、都市近代化は、子供たちを郊外に流出させてしまった。
商店街から、居住空間&働く場所を併せ持った、生活街への変換が必要。
街を歩く、酒を酌み交わす、色々なコミュニケーションの中に、宝を発見する機会がある。
[武者] 三橋さん・・・外から見た松本のビジョンは?
[三橋] 松本の人達は、シティープライドが高い。(高かった。)
近年、そのプライドが低くなっているように感じる。これは、近代化の弊害のひとつ。
プライドの源泉は、松本城や山岳景観にあるのだろうが、
山岳景観を守れないのも、シティープライドが低くなった原因であり、その結果。
高松丸亀では、築城400年祭を契機に、500年祭に向けたまちづくりビジョンを掲げた。
ビジョンは100年を視野にいれつつ
一方で、とりあえず10年後は・・・という小さな積み重ねが必要。
[武者] 少なくとも10年先を・・・と考えていく発想。
時間の関係で、三つ目の論点「協働と組織化」に入れなくて残念だが・・・三橋さん・・・最後にカタクラモールのあるべき姿は?
[三橋] カタクラモールは、企業(カタクラ工業)が社会貢献として考えるべき問題。
中心市街地にあっては、市民と共に、市民に支持される事、歴史性を大切にする事。
オープンなスタイルで、街なかの人と交流できる形の開発を望む。
即ち、「街なか観光都市」の発想を持つべき。
松本は自転車にやさしく、路地や湧水・水路が豊富、それらの都市資源を大切に。
カタクラ工業は、企業理念として、これに対する理解がある筈。
新しい松本のライフスタイルセンターの創出、「商店街」から「生活街」への変換。[武者] 大きなヒントを有難うございます。
皆さん、今日は、有難うございました。
三橋さんの貴重な基調講演
「脱近代化」がサブテーマになったパネルディスカション
コーディネーターの武者先生が、最初からキレていて
聞きごたえのあるシンポジウムになりました。
120名程の方にお越しいただきました。
本当にありがとうございました。
以下「松本都市デザイン学習会」山田さんが書いて頂いた議事録です。
◆松本まちづくりシンポジウム◆
「中心市街地の問題とこれからの松本ビジョン」
日時 8月29日(月) 19時~21時
場所 松本市中央公民館 6階ホール
主催:ナワテ通り商業協同組合+なわて通りプロジェクト
共催:松本都市デザイン学習会・松本市中央公民館
参加者:120名

●第1部
基調講演「中心市街地の問題とこれからのまつもとビジョン」」講師:三橋重昭(NPO法人まちづくり協会理事長 経済産業省商店街再生ネットワーク専門委員
中心市街地商業活性化アドバイザー)
松本は、何度か訪れているが、松本城・山岳景観・文化の香り豊かな印象を持っている。
この講演では、全国の事例を交えながら、これからの松本のまちを考えていきたい。
講演は、以下の項目に沿って話を進める。
・なわて商店街の印象・評価・課題
・小石川の新しいまちづくりの取り組み「小石川マルシェ」
・松本市の商業構造
・松本市の中心市街地を考える 脱近代化・脱商店街活性化
・カタクラモール
松本の中心市街地を歩いて、小路や蔵の街の佇まいのヒューマンスケールに感動した。
しかし、昭和50年代の区画整理された駅前地区には、商業中心の活発な印象が無い。
また、伊勢町を中心とした区画整理地区の商業者は、近代化建替えによる負債で疲弊があるだろう。
六九町は、商店街が廃れた街として、知られている。
この様に、松本は、美しい街である一方、多くの問題も抱えている。
●なわて商店街の印象・評価・課題東京商工会議所の商店街評価、370項目に従って、なわて商店街を分析してみた。
まち並みの魅力/4.45 まちの歩きやすさ/4.56 まちの使い易さ/4.50
まちの楽しさ賑わい/4.07 日常利便/2.83 広域集客/3.75 公益的整備/3.89
全国の商店街と比べても、高評価と言える。
特色としては、通年の昼間歩行者天国。歩いて楽しい魅力がある。
歩行者通行量も5000人~7000人と、松本中心市街地で7位/14調査
人口20万人の商店街として、とても高い数値(上田市の最高で2000人)
但し、店舗の月坪効率は10.1万円と低く、営業力強化が課題。
しかし、松本市全体売り上げの0.1%の小さな商店街が、
この様なシンポジウムを開く前向きな態度は、特筆すべき。
●小石川の新しいまちづくりの取り組み文京区公設市場など、S30年代までは、賑わっていた商店街の歴史がある。
バブル期の地上げ、マンション建設があったが、商店街はある程度存続してきた。
エンマ通り商店街は、現在、22店で、年間10億円の売り上げ。
4つの商店街があるが、もっと頑張れる筈である・・・新しいまちづくりの取り組みスタートのきっかけ。
若手の商店主を集め、H22年「小石川活性化研究会」・ワークショップを始める。
歴史と現状分析から、10年後の小石川を考え目指すべき姿をまとめる。
・ちょっといい普段(少し上質な生活)
・文京の玄関(後楽園に近接・地下鉄4線・コミュニティーバスの発着)
ビジョンを推し進めるプロジェクト「小石川マルシェ」
・「ちょっといい普段」を念頭に、産直の食材市場。源覚寺の境内で、700人 30万円の売り上げ。
・60代、70代が中心の既存商店街に対して、マンション居住の若い世代にアピールできた。

●松本の小売商業構造・松本全体、年間売上高3239億円、月坪効率は25.5万円で、ほぼ全国平均。
・郊外ロードサイド(国道19号沿い)年間売上高1203億円で、月坪効率28.9万円と高い。
・駅前・中心市街地は月坪効率15万円~20万円と落ち込んでいる。
この分析から、現在は郊外ロードサイドが商業的には中心である、という印象。
ショッキングな数値だが、松本商工会議所の統計・分析でも、この事実は認識されていない。
「松本市の中心市街地商業ビジョン」を拝見したが・・・
個店の魅力向上・・・個店が厳しい状態の中で、個店の頑張りに期待するのは非現実的。
人材・組織の構築・・・活性化基本計画から10年を経た現在でも、なされていない。
「商都松本」というおごりも過去のもので、現在の市民はそう思っていない筈。
中心市街地活性化基本計画も策定されていない。(県内では、長野・飯田・塩尻・上田が策定)
中心市街地活性化基本計画が必ずしも功を奏すとは言えないが、
金沢は行政を中心に成功、高松は丸亀商店街を中心に成功・・・成功例もあり、取り組む価値はある。
日本の商業全体で、商店数が減少し、大型店化する中で、
公共・民間・市民がタッグを組んだ新しいスタートが必要。
脱近代化(国土交通省主導の、車優先・道路拡幅・核店舗・共同化ビル等の都市近代化からの脱却)
脱商店街活性化(店が減り商店主が高齢化した中で、活性化は望めない)
やはり、中心市街地商店街は、活力が無ければならない。
●松本のビジョン・街なか観光・・・まちの資産を活かす。交流人口を増やす。 街なか観光の事例・・・長崎さるく博
・新しいレベルの組織(×商工会議所・×商連・×縦割り行政)
・ローカルイニシアチブ(松本市民がベースに)
・カルチャーハプニング(路地など都市の魅力の再発見・SKF・工芸の五月etc)
・アーバンネイバーフード(都市の中で新しい近隣を育てる)
・メインストリートプログラム(組織デザイン・経済活性化プロモーション)
・商店街から、生活街への脱却
●カタクラモール構想カタクラ工業大宮工場跡地のコンサルタント経験から、カタクラの街に対する良心は信じたい。
松本における8.36haの土地は、街なかと一緒に考えていくべき。
事例としては、ライフスタイルセンター(アメリカ)等が注目される。
カタクラを中心市街地の構成メンバーとして、
中心部 VS 郊外 の構図の中で考えるべき。
世界に誇れる、松本の中心市街地を構築していって欲しい。
●松本市の取り組みの紹介
「水辺のマルシェ」
発表者:上條(なわて通りプロジェクト「水辺のマルシェ」プロジェクトリーダー)
8月に、なわて商店街 女鳥川を舞台に、「水辺のマルシェ」を実施
「NO―JIN」という松本の若手農業者を中心とした組織を発足
農業をアート、農作物・農業加工品をアート作品として展開している。
対面販売(コミュニケーション)を大切に、新たな可能性を探っていきたい。
「水辺のマルシェ」では、多分野の人と協働し、
食卓プロデュースとして、食材・器・雑貨etc をトータルで提案したい。
今後、年内に4回の「水辺のマルシェ」を企画している。

●第2部:パネルディスカションコーディネーター:武者忠彦(信州大学経済学部准教授)
パネリスト:三橋重昭(NPO法人まちづくり協会理事長)
丸山悦男(前松本市建設部長)
倉澤 聡(都市計画家 工芸の五月事務局 松本都市デザイン学習会会員)
山本真也(ナワテ通り商業協同組合理事長)
[武者] パネルディスカッションでは、基調講演を踏まえ3つの論点で議論を展開したい
1.「都市の近代化」の終わり・・・なわて商店街から考える潮流の変化
2.ビジョンを考えるヒント・・・「時間限定」「地域性」「外部環境」
3.協働と組織化・・・ビジョンへのアプローチ
最初の論点、「近代化」は、ハード中心・グローバリズムの考えで進められてきたが、山本さん・・・なわて商店街の実践をとおして、どの様に感じているか?
[山本] なわて商店街で「カエルまつり」を行って10年になる。
信大・松大+商店主を主体として実践、全国でもめずらしい推進体制で進めてきた。
[武者] 新しいまちづくり主体の重要性を感じる。
丸山さん・・・行政から見たなわて商店街は?
[丸山] 松本市建設課でH3~なわて商店街に関わってきた。
S63「ふるさとの川」に認定され、H3事業許可。
武家地と商人町の境に明治期に四柱神社がつくられ、神社の露店として、なわてが始まる。
子供のころから、神道まつりの舞台として、女羽川の遊びとして、個人的な思い入れがある。
なわて商店街の魅力を再発見してみた
・水辺の行事と風物詩・・・女羽川、三九郎
・道幅の狭さ・・・商店主と買い手のコミュニティーを生む
・カエル・・・ユニークなキャラクターの存在
・通年昼間歩行者天国・・・人が主人公の町
建設にあたっては、河川法・道路法・建築基準法など、法規制のクリアに奔走した
特に、河川法に於いては、治水安全度と親水性の狭間で、国土交通省と様々な議論。
[武者] 風土・風物との連帯、法規制をクリアする熱意、これがポイント。
倉澤さん・・・工芸の五月の新しさは? 海外経験を通して?
[倉澤] 工芸の五月は、5年前に発足し、松本市と協働して3年になる。
クラフトフェアが前身であるが、交通渋滞・環境負荷など、迷惑イベントの側面もあった。
交通社会実験などを通して、市民に広く受け入れられるイベントに発展した。
多分野との協働が結果としてまちづくりに・・・これからのまちづくりでは、協働が大切。
都市近代化=車社会から脱却し、人が歩く、集まる、カルチャーハプニングが生まれる町に。
フランスに5年前に生活していたが、中心市街地に人が戻りつつある。
海外では、いち早く、都市近代化からの脱却がみられた。
[武者] 工芸の五月・クラフトフェアは自主的な草の根からの展開。
そこでは、主催者自らが活動を楽しんでいる様子が伝わる点が重要。
飴市・松本ぼんぼんも、かつては主催者の熱意があっただろうが・・・。
海外でも、歩ける街が大きな潮流になっている。
三橋さん・・・全国の潮流は? 事例なども・・。
[三橋] なわて商店街で参考になる事例として、伊勢のおかげ横丁がある。
赤福の社長がマネージメントしている通りだが、全国トップクラスの売場効率。
いすず川との一体感など、なわて商店街と通じるところがある。
なわて商店街は、「地域のニーズに合理性」があり法律が運用されたと考える。
川越・小布施・裏原宿の例で解る様に、「都市は人間の為にある。」
おかげ横丁は、一主体(赤福)による民間のマネージメントなので特殊例だが、
商店街のマネージメントに於いて、「やる気の無い店は去れ」という態度も大切。
商店街のリーダーには、個店と街の調整役を超えた、発想の切り替えが必要。
街のハードの近代化と共に、街のマネージメントの近代化、
「ディベロップからマネージメントへ」が重要。

[武者] 「ディベロップからマネージメントへ」は大切なキーワード。
基調講演でも話題になった「松本の商業ビジョン」を拝見したが、
私は、「松本」という単語が無い事に、地域性とビジョンの欠如を感じる。
若者は郊外ロードサイド中心、中心市街地とは何か? 世代による認識の相違も感じる。
二つ目の論点「ビジョンを考えるヒント」に関して、以下のキーワードを挙げる。「時間設定」・・・世代、時間のスパンの捉え方。10年後or 100年後?
「地域性」・・・松本では、どうする。
「外部環境」・・・経済動向、トレンド、低成長、震災後の日本を捉えて
これらを踏まえて、「ビジョンを考えるヒント」のアイデアを伺いたい?
[山本] 「なわて通りプロジェクト」を、市民・商店主・行政とでタッグを組んで考えてきた。
「なわて」を「松本」と置き換えて考える事でヒントが出てくるのでは・・・。
なわて商店街では、「道で遊ぶ」という理念・・・これは松本ビジョンのヒント。
[武者] 「道で遊ぶ・通りで遊ぶ」・・・松本らしさを感じる。コンパクトシティーの根拠になろう。
[倉澤] 地域性が、全国・海外への発信力を持つ。
松本の良さのひとつに、市街地に川が流れている点を挙げる。
私は、この頃、アレチウリの駆除に奔走しているが・・・皆、川を大切にしない。
湧水は、ここ何年かで認知され活かされてきている。
川も同様に大切にし、宝(都市資源)を磨く事が大切。
山岳景観も同様で、50年タームの都市を考えると、高層マンションは問題が多い。
[武者] 今の街の良さ=地域資源を活かす。アレチウリへの取り組みも50年タームの取り組み。
丸山さん・・・50年・100年タームでの取り組みは?
[丸山] 歩く街・歩ける街が、街を変えていく。
松本市でも、車社会から、人を主体にした街への転換を図っている。
なわて商店街でウォーキングをする親子の姿が微笑ましい。
それに対して、都市近代化は、子供たちを郊外に流出させてしまった。
商店街から、居住空間&働く場所を併せ持った、生活街への変換が必要。
街を歩く、酒を酌み交わす、色々なコミュニケーションの中に、宝を発見する機会がある。
[武者] 三橋さん・・・外から見た松本のビジョンは?
[三橋] 松本の人達は、シティープライドが高い。(高かった。)
近年、そのプライドが低くなっているように感じる。これは、近代化の弊害のひとつ。
プライドの源泉は、松本城や山岳景観にあるのだろうが、
山岳景観を守れないのも、シティープライドが低くなった原因であり、その結果。
高松丸亀では、築城400年祭を契機に、500年祭に向けたまちづくりビジョンを掲げた。
ビジョンは100年を視野にいれつつ
一方で、とりあえず10年後は・・・という小さな積み重ねが必要。
[武者] 少なくとも10年先を・・・と考えていく発想。
時間の関係で、三つ目の論点「協働と組織化」に入れなくて残念だが・・・三橋さん・・・最後にカタクラモールのあるべき姿は?
[三橋] カタクラモールは、企業(カタクラ工業)が社会貢献として考えるべき問題。
中心市街地にあっては、市民と共に、市民に支持される事、歴史性を大切にする事。
オープンなスタイルで、街なかの人と交流できる形の開発を望む。
即ち、「街なか観光都市」の発想を持つべき。
松本は自転車にやさしく、路地や湧水・水路が豊富、それらの都市資源を大切に。
カタクラ工業は、企業理念として、これに対する理解がある筈。
新しい松本のライフスタイルセンターの創出、「商店街」から「生活街」への変換。[武者] 大きなヒントを有難うございます。
皆さん、今日は、有難うございました。
Posted by 水辺プロジェクト at
◆2011年09月10日09:48
│シンポジウム




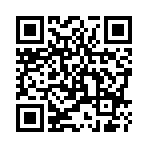

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。